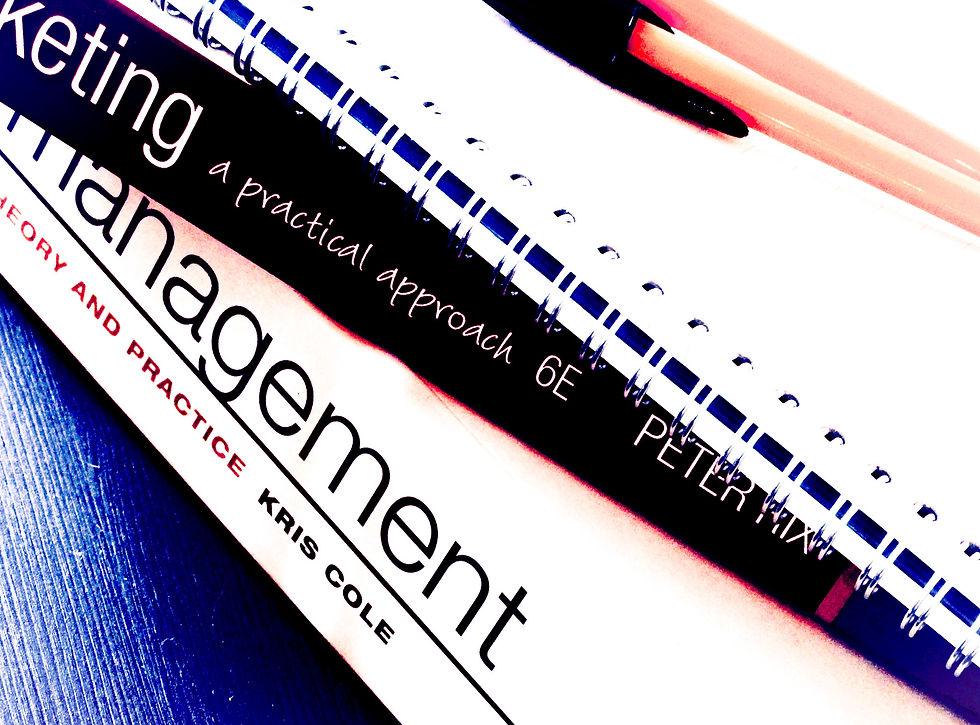アッベの法則
- 深沢 光

- 5月5日
- 読了時間: 1分
更新日:5月17日
アッベの法則は、「測定はできるだけ対象物が作用する地点の近くで行うべき」という測定精度に関する重要な原理です。ドイツの物理学者エルンスト・アッベが提唱し、測定対象物と測定器の目盛を測定方向の同一直線上に配置することで、誤差を最小限に抑えられるとされています。
具体例として、外側マイクロメータとノギスの違いが挙げられます。マイクロメータは、測定対象物と目盛が一直線上に配置されているため、アッベの法則を満たし高い精度で測定できます。一方、ノギスは目盛と測定位置が離れているため、わずかな角度ズレ(θ)や距離(a)があると「アッベエラー」と呼ばれる誤差が生じやすくなります。例えば、ノギスでa=10mm、θ=0.01radの場合、誤差e=aθ=0.1mmとなり、マイクロメータの誤差(0.005mm)に比べて大きくなります。
また、三次元測定機でもプローブと基準スケールが一致していない場合、アッベエラーによる測定誤差が発生します6。このように、アッベの法則を意識することで、測定精度の向上や誤差低減が可能となり、ものづくりや品質管理の現場で非常に重要な役割を果たしています。